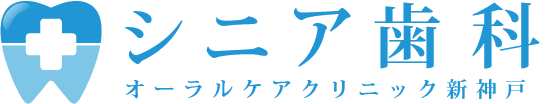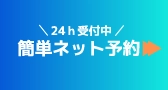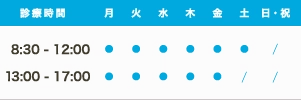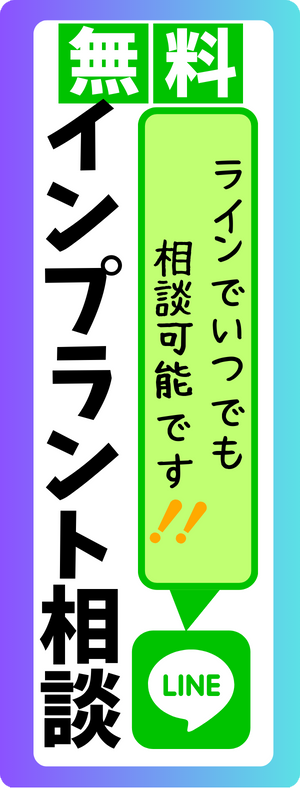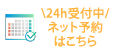こんにちは。兵庫県神戸市中央区の歯医者、シニア歯科オーラルケアクリニック新神戸 院長の小松原 秀紀です。
歯を失ってしまい、日常生活で不便を感じている方にとって、「入れ歯(義歯)」は、噛む機能や見た目を回復させるための、非常に重要な治療選択肢の一つです。しかし、特に質の高い快適な入れ歯を求めると、それなりの費用がかかることも事実です。「入れ歯を作りたいけれど、費用が心配…」そんなお悩みを抱えている方も少なくないのではないでしょうか。
先日、患者様から「入れ歯の費用って、確定申告で安くなったりするんですか?」というご質問をいただきました。これは、治療費の負担を少しでも軽減したいと願う方にとって、非常に大切なポイントです。結論から申し上げますと、入れ歯治療にかかった費用は、国の税制度である「医療費控除」の対象となり、手続きをすれば税金が還付される(戻ってくる)可能性があります。
今回は、この「入れ歯と医療費控除」について。どのような入れ歯が対象になるのか、保険と自費で違いはあるのか、そして具体的にどのくらいの負担軽減が見込めるのか、知らないと損をしてしまうかもしれない、節税のポイントを詳しく解説していきます。
目次
- そもそも「医療費控除」とは?基本のキを理解しよう
- 【結論】入れ歯治療は医療費控除の対象になります!保険・自費の違いは?
- 保険の入れ歯と自費の入れ歯:それぞれの特徴と控除額への影響
- いくら戻る?控除額と還付金の計算方法を具体例でシミュレーション
- 家族全員分を合算!申請を忘れないためのポイントと手続きの流れ
- まとめ
1. そもそも「医療費控除」とは?基本のキを理解しよう
まず、「医療費控除」という制度そのものについて、基本的な仕組みをご説明します。多くの方が誤解されているのですが、これは「支払った医療費が、そのまま現金で返ってくる」制度ではありません。医療費控除とは、1年間(その年の1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計額が、原則として10万円(※)を超えた場合に、その超えた金額(上限200万円)を、税金の計算の元となる「所得」から差し引くことができる(控除できる)制度のことです。「所得控除」の一つであり、所得が低くなった結果として、納めるべき所得税が安くなり、払い過ぎていた分が還付金として戻ってくる、という仕組みなのです。さらに、翌年度に支払う住民税も安くなるという、二重のメリットがあります。この制度は、高額な医療費がかかった家計の負担を少しでも和らげるために国が設けている、国民のための大切な権利ですので、対象となる場合はぜひ活用したいものです。そして、この医療費控除の大きな特徴の一つが、ご自身だけでなく、「生計を一にする配偶者やその他の親族」のために支払った医療費も、すべて合算して申告できるという点です。例えば、ご自身の治療費、奥様の治療費、お子様の矯正費用、ご両親の入院費など、家族全員分の医療費をまとめて、ご家族の中で一番所得の多い方が申告することで、最も効率的に税金の還付を受けることができます。(※その年の総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく、総所得金額等の5%を超えた場合となります。)この仕組みを理解しておくことが、賢く制度を活用するための第一歩です。入れ歯治療も、決して安価ではない医療行為ですので、この制度を念頭に置いておくことは非常に重要になります。
2. 【結論】入れ歯治療は医療費控除の対象になります!保険・自費の違いは?
さて、本題の「入れ歯治療は医療費控除の対象になるのか?」という点について、明確にお答えします。はい、入れ歯(義歯)の作製にかかった費用は、医療費控除の対象となります。 これには、保険が適用される入れ歯はもちろんのこと、より快適さや審美性を追求した自由診療(自費)で作製した入れ歯も含まれます。
国税庁では、医療費控除の対象となる医療費を「治療を目的として支出したもの」と定めています。例えば、歯を白くするためのホワイトニングや、見た目の改善だけを目的としたセラミック治療などは、「美容目的」とみなされ、原則として対象外となります。しかし、入れ歯治療は、失われた歯の「咀嚼機能(噛む機能)を回復させる」という、生活を送る上で不可欠な機能を回復させるための、明確な「治療目的」があります。また、歯がない状態を放置することによる、残った歯の移動や傾斜、それによる噛み合わせの崩壊を防ぐという、予防的な側面も持っています。したがって、入れ歯治療は、その材質や費用に関わらず、医療費控除の対象となる「医療行為」として、きちんと認められているのです。ですから、保険の入れ歯はもちろんのこと、「金属床義歯」や「ノンクラスプデンチャー」といった、より高機能な自費の入れ歯を作製した場合でも、その費用は全額、医療費控除の対象として申告することが可能です。これは、治療の選択肢を広げる上で、非常に心強い情報ではないでしょうか。入れ歯の調整や修理にかかった費用、さらには入れ歯安定剤などの購入費用も、治療に関連するものとして認められる場合がありますので、領収書は大切に保管しておきましょう。
3. 保険の入れ歯と自費の入れ歯:それぞれの特徴と控除額への影響
入れ歯には、保険適用のものと、自費診療のものがあります。どちらも医療費控除の対象ですが、それぞれの特徴と、控除額への影響について見ていきましょう。
- 保険適用の入れ歯(レジン床義歯など)
- 特徴:主にプラスチック(レジン)で作られ、部分入れ歯の場合は金属のバネ(クラスプ)で固定します。
- メリット:最大のメリットは、費用負担が少ないことです。健康保険が適用されるため、自己負担は1割~3割で済みます。
- デメリット:使用できる材料や設計に国の定めたルールがあり、機能性や審美性に限界があります。例えば、床(歯茎に接する部分)が厚くなりやすく、違和感や話しにくさを感じたり、食べ物の温度が伝わりにくかったりします。また、金属のバネが見た目に気になることもあります。
- 治療期間:比較的短く、型取りから完成まで約1ヶ月程度が目安です。
- 医療費控除:窓口で支払った**自己負担額(1割~3割)**が控除の対象となります。
- 自由診療(自費)の入れ歯
- 特徴:材料や設計に制限がなく、患者様のお口の状態やご希望に合わせて、オーダーメイドで作製されます。代表的なものに、床に金属(チタンやコバルトクロム)を使用した「金属床義歯」や、金属のバネがない「ノンクラスプデンチャー」、特殊な維持装置を用いた「コーヌスクローネ」などがあります。
- メリット:薄くて丈夫なため違和感が少なく、適合性が高いため安定して噛めます。金属床なら食べ物の温度が伝わりやすく食事が美味しく感じられます。ノンクラスプデンチャーなら見た目が非常に自然です。総じて、保険の入れ歯に比べて、快適性、審美性、機能性が格段に向上します。これは、日々の食事や会話の質を高め、精神的な満足感にも繋がる大きなメリットです。
- デメリット:健康保険が適用されないため、費用が高額になります(数十万円~)。
- 治療期間:精密な工程を経て作製されるため、保険の入れ歯より少し長くかかり、約1ヶ月半~2ヶ月程度が目安となることがあります。
- 医療費控除:支払った治療費の全額が控除の対象となります。そのため、高額ではありますが、医療費控除による税金の還付額も大きくなる可能性があります。
どちらの入れ歯を選ぶかは、費用だけでなく、ご自身のライフスタイルや、入れ歯に求める快適さなどを総合的に考慮して決めることが大切です。そして、どちらを選んだとしても、医療費控除の対象となることを覚えておきましょう。
4. いくら戻る?控除額と還付金の計算方法を具体例でシミュレーション
では、実際に医療費控除を申請すると、どのくらいの金額が戻ってくる(還付される)のでしょうか。具体的な計算方法と、シミュレーションを見てみましょう。
まず、控除の対象となる金額(医療費控除額)を計算します。 医療費控除額 = ( 実際に支払った年間の医療費合計額 - 保険金などで補填された金額 ) - 10万円 (※年間所得200万円未満の場合は10万円ではなく所得金額の5%)
次に、この医療費控除額に、ご自身の所得税率を掛けて、還付される所得税額を計算します。 所得税の還付金額(目安) = 医療費控除額 × 所得税率
さらに、医療費控除を申請すると、翌年度の住民税も安くなります。 住民税の減額分(目安) = 医療費控除額 × 10%(住民税率)
【シミュレーション例:課税所得500万円の方が、50万円の自費の入れ歯を作製した場合】
- 年間の医療費合計:50万円(入れ歯費用のみと仮定)
- 保険金などからの補填:0円
- 課税所得:500万円(所得税率20%)
① 医療費控除額の計算 (50万円 - 0円)- 10万円 = 40万円
② 所得税の還付金額(目安)の計算 40万円 × 20% = 8万円
③ 翌年度の住民税の減額分(目安)の計算 40万円 × 10% = 4万円
このケースでは、確定申告を行うことで、所得税が約8万円還付され、さらに翌年の住民税が約4万円安くなる、つまり合計で約12万円もの経済的負担が軽減される計算になります。これは非常に大きな金額であり、高額な自費の入れ歯を選択する際の、大きな後押しになるのではないでしょうか。ご自身の所得税率は、源泉徴収票などで確認できますので、ぜひ一度、ご自身のケースで試算してみてください。
5. 家族全員分を合算!申請を忘れないためのポイントと手続きの流れ
医療費控除を最大限に活用し、確実に申請を行うために、いくつかの重要なポイントと手続きの流れを確認しておきましょう。
- 家族全員分の医療費を合算する:繰り返しになりますが、これが最も重要なポイントです。ご自身の入れ歯費用だけでなく、配偶者やお子様、同居または仕送りなどをしているご両親など、「生計を一にする」家族全員が、その1年間に支払った全ての医療費(病院の治療費、薬代、通院交通費など)を合計して申告できます。
- 所得が一番多い人が申告する:家族の中で所得税率が最も高い方が代表して申告することで、還付される金額が最も多くなります。共働きのご夫婦の場合は、所得の多い方がまとめて申告するようにしましょう。
- 領収書は必ず保管する:医療費控除の申請自体には、領収書の提出は不要になりましたが、「医療費控除の明細書」を作成する際に必要ですし、税務署から提示を求められた場合に対応できるよう、5年間は自宅で大切に保管しておく義務があります。年ごとにまとめて、分かりやすく整理しておきましょう。
- 申請期間と方法:医療費控除の申請は、確定申告によって行います。申告期間は、治療を受けた翌年の2月16日から3月15日頃までです(還付申告だけであれば、翌年1月1日から5年間可能です)。お住まいの地域を管轄する税務署に直接書類を持参するか、郵送、あるいは国税庁のウェブサイト「e-Tax」を利用して電子申告することも可能です。会社員の方も、年末調整では医療費控除は行われないため、ご自身で確定申告を行う必要があります。
- 必要なもの:「医療費控除の明細書」(国税庁HPで作成可能)、源泉徴収票(会社員の場合)、マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)、還付金を受け取る銀行口座の情報などが必要です。
- 支払い方法に関する注意点:入れ歯費用をデンタルローンやクレジットカードで支払った場合も、医療費控除の対象となります。その場合、ローン契約が成立した年、またはクレジットカードで決済した年に、治療費の全額をその年の医療費として申告します。毎月の返済額を申告するわけではない点にご注意ください。信販会社の契約書やカード利用明細書が、支払いを証明する書類となります。
- 交通費も忘れずに:通院のために利用した公共交通機関(電車、バス)の交通費も医療費控除の対象となります。日時、医療機関名、交通費、利用した交通機関名を記録しておきましょう。(※自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です)
6. まとめ
入れ歯治療と医療費控除について、ご理解いただけましたでしょうか。最後に、大切なポイントをもう一度おさらいします。
- 入れ歯治療は、保険適用・自由診療(自費)に関わらず、医療費控除の対象です。
- 失われた噛む機能を回復させる「治療目的」だからこそ、対象となります。
- 特に自費の入れ歯は高額ですが、医療費控除による税金の還付額も大きくなり、実質的な負担を軽減できます。
- 家族全員分の医療費を合算し、一番所得の多い人が申告するのが最もお得です。
- 領収書は必ず5年間保管し、治療を受けた翌年に忘れずに確定申告を行いましょう。
入れ歯治療は、あなたの「食べる」「話す」「笑う」といった、生活の根幹を支える大切な治療です。費用面での不安から、治療をためらったり、妥協してしまったりするのは、非常にもったいないことです。医療費控除という制度を賢く利用することで、経済的な負担を軽減し、ご自身が本当に納得できる、より質の高い入れ歯を選択する一助となれば幸いです。
当院では、患者様一人ひとりのお口の状態やご希望、ご予算に合わせて、最適な入れ歯治療をご提案するとともに、医療費控除などの費用に関するご相談にも、丁寧に対応させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。